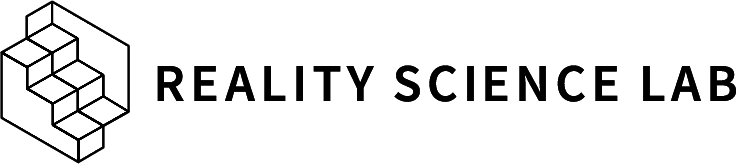現実科学ラボでは、各分野で活躍している専門家とともに「現実とは?」について考えていくレクチャーシリーズを2020年6月より毎月開催しています。
第5回となる今回は、2020年10月20日、建築家、作家、アーティストの坂口恭平さんをお迎えしました。さらにスペシャルゲストとして、バイオアーティストである福原志保さんにも議論に加わっていただきました。
本記事では、当日の簡単なレポートをお届けします。

https://reality-science005.peatix.com/?lang=ja
現実科学とは
坂口恭平さん

1978年、熊本県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。2004年に路上生活者の住居を撮影した写真集『0円ハウス』(リトルモア)を刊行。以降、ルポルタージュ、小説、思想書、画集、料理書など多岐にわたるジャンルの書籍、そして音楽などを発表している。2011年5月10日には、福島第一原子力発電所事故後の政府の対応に疑問を抱き、自ら新政府初代内閣総理大臣を名乗り、新政府を樹立した。躁鬱病であることを公言し、希死念慮に苦しむ人々との対話「いのっちの電話」を自らの携帯電話(090-8106-4666)で続けている。近刊に『建設現場』(みすず書房)、『cook』(晶文社)、『まとまらない人』(リトルモア)など多数。
砂の声
幼少の頃、福岡県にある電電公社の社宅に住んでいました。少し離れたところには漁師町がありました。団地と漁師町の間に、何か境界があるように感じられました。漁師町へ続く道は砂利なのですが、社宅の団地はコンクリートで整えられていました。植栽も整えられていました。
団地のコンクリートから砂利道へ一歩踏み出すと、ホームから離れた不安感のような感覚とともに、土の上で生きる人としての歓びが確かにありました。
4、5歳の頃の僕は、ウスバカゲロウの幼虫である蟻地獄が好きでした。しかし蟻地獄は、少し離れた白浜の方の砂にはいるのに、うちの団地にはいなかった。何で同じ砂なのに、蟻地獄は片方にしかいないのか?それを調べるために僕がエビデンスとしたのは「声」でした。人ではない、砂の声です。当時の僕は、人と同じように、砂の声を聞いていたのです。
砂は「私たちは別のところから運ばれてきたのです。」とすすり泣いていました。その時、僕は「ここ」にある砂や石を、無闇に、人の勝手な思いつきで別のところへ持って行ってはいけないのだと強く感じました。

今になっても僕はどうしても、資本主義だとか、米国の企業がどうとか、そういう話がうまく頭に入ってこないのです。それよりも砂と対話することの方がずっと自然に感じるのです。そういうわけで僕は最近、畑を始めました。
畑を始めたその時、砂が「Welcome back」と僕に語りかけてきました。記憶なのか、妄想なのか、夢なのか、現実なのか、もはや何だったのかわからないけれど、確かにその声を聞いたのです。
思えば土というのは、僕にとって常に大きな問題として現れてきました。
なぜ土地を所有して「良い」のか?
思えば高校生の時も、先生に「なぜ土地を所有していいのか?」と質問をして困らせていました。先生は「それは税金を払うためであり……」と近代資本主義のようなのことを僕に植え付けようとしてきますが、依然として僕には全く分かりませんでした。
猫にも風にも、土地を「所有する」という観念はないのに、なぜ人間だけが土地を所有していいんでしょうか?どんな法律を探しても、土地の所有を人間に許可するような証拠は見当たりません。
そんな根本の原理が成立していない以上、僕は建築をすることができませんでした。周りの人たちは当たり前のように「土地を所有する」という現実を生きているけれども、僕にはそれは現実ではないように思われるのです。
現実なんて、ない。自然を所有することは、できない。みんなが勝手に現実だと思い込んでいるものは、ハリボテに過ぎない。現実が「生音」だとすると、多くの人は周波数がカットされ、加工された後のmp3を現実(生音)だと思い込んでいるように感じます。本当は生音となる周波数の波がそこら中にあるのだから、加工することなしにそのまま受け取ることはできないのでしょうか。
茄子が救った女の子
僕は「いのっちの電話」という、死にたい人であれば誰でもかけることができる電話サービスを、2012年から無料でやっています。本家となる「いのちの電話」がほとんどつながらないという現状を知って、一人で勝手にはじめました。
ある日、19歳の女の子から電話がかかってきました。僕は、「最後に俺のお願いを聞いてくれないか」と彼女に言いました。
「まず、お母さんは家庭菜園とかやってない?」
「やってます」
「いいね、今生存率がグッと上がったぞ。畝の中に、両手を手首まで入れて、30分過ごしてからまた電話してくれる?」
そういって電話を切ると、30分後にまた電話がかかってきました。
「やってきました。何も変わりませんでした、もう死んでいいですか?」
「今のは挨拶だから。畝に手を入れるっていうのは、畝の心の中に手を入れるようなもので、これで向こう(畝)は君の手の匂いを感じた。次にお前が近づいたら、声を放つから聞いてみてほしい。家庭菜園では何を育ててるんだっけ?」
「茄子です」
「その茄子さんに聞いてみろ。私はどうやったら死ねますか?って」
そこで電話をまた切りました。

2分後、再び電話がかかってきました。
「どう声、聞こえた?」と尋ねると、「はい」という返事!
「茄子はなんて言ってたの?」と尋ねたら彼女はこう言いました。
「今じゃないんじゃない?」
茄子、グッジョブ!
本当に聞こえたのかと確認をすると彼女は本当に聞こえたと言うのです。
こういったことが、僕の現実には起きます。
坂口さんにとっての「現実とは?」
現実なんてものは、ない!
おわりに
スライドを全く使わない、淀みのないトークは、この後もしばらく続きました。トークの終了後にはバイオアーティストの福原志保さんにも加わっていただき、自由なパネルティスカッションを行いました。