デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。
「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。
Twitterのハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。
概要
- 開催日時:2023年11月20日(月)19:30~21:00
- 参加費用:無料
- 参加方法: Peatixページより、参加登録ください。お申込み後、Zoomの視聴用リンクをお送りいたします。
視聴専用のセミナーになりますので、お客様のカメラとマイクはオフのまま、お気軽にご参加いただけます。
ご注意事項
- 当日の内容によって、最大30分延長する可能性がございます。(ご都合の良い時間に入退出いただけます。)
- 内容は予期なく変更となる可能性がございます。
- ウェビナーの内容は録画させていただきます。
プログラム(90分)
- はじめに
- 現実科学とは:藤井直敬
- ゲストトーク:樋口真嗣氏
- 対談:樋口真嗣氏× 藤井直敬
- Q&A
登壇者

樋口真嗣
映画監督・特技監督。1965年9月22日生まれ。 1984年「ゴジラ」にて映画界入り。95年「ガメラ 大怪獣空中決戦」で特技監督を務め、「日本アカデミー賞特別賞」を受賞。庵野秀明監督と共に、「エヴァンゲリオン」シリーズなど数多くのヒット映画作品に画コンテやイメージボードとして参加。主な監督作品は「ローレライ」「日本沈没」「のぼうの城」「進撃の巨人2部作」など。

藤井 直敬
株式会社ハコスコ 取締役 CTO
医学博士/XRコンソーシアム代表理事
ブレインテックコンソーシアム代表理事
東北大学医学部特任教授
デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授
MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。
共催
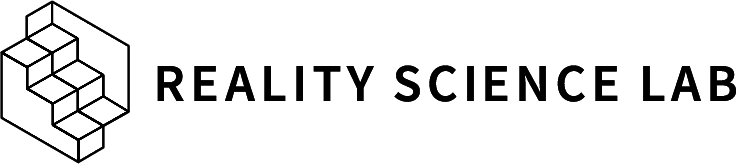
※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。
“物語”はこれからの私たちの世界を支える豊かさ
藤井 はじめに、いつもの通り現実科学とはなんだ?ということを簡単にお話しします。僕らは普段、科学的な世界観の中で生きています。目に見えている万人に共通の現実が存在していて、私たちはそれを見て、聞いて、共有することが当たり前にできている。
これ自体は全然悪いことではないんですけれど、人間の本質とフィットしているかというと、どうもそうではない。壁のシミが人の顔に見えるとか、無意識が作る、脳が勝手に感じているもの。そういったものが神話的な世界観として、現実の一部として存在している。
こういう世界がおそらく、人間の本質的な世界観だと思うんですね。これは共有することは難しいけれど、その分、非常に豊かで多様性を持った世界です。ここに人工的な現実というのが、それと分からないように重なってきているのが、いま起きていることです。
この人工的な現実と基底現実の間で、無尽蔵に色々なクリエイティビティが生まれてくる。日常生活の中で、それを物語として食べて生きていく。そういう新しい世界観の中で、私たちの生活、暮らしはもっと豊かになるんじゃないかというのを、僕は希望として抱いています。
今日は、樋口真嗣監督という、存在しない世界を僕らの目の前に届けてくれる、特撮の神様みたいな方がいらっしゃっていますので、これから皆さんとお話をうかがいたいと思います。
現実と虚構の境界で
樋口 よろしくお願いします。それで言うと、私のやっている仕事は本当に現実じゃなくてもいいですよっていう世界なので。
藤井 そういう点では虚構なんだけれども、そこにもやっぱり、その中の現実があるのではないですか?
樋口 ええ。ですから、そういった意味ではかなり境目で生きてきたなという気がしたので、今回改めてそういう切り口で自分の仕事だったり、自分がなぜこれを目指したのかということを考え直す機会になったと思います。
私は映画監督という肩書きではありますが、あまり普通の映画というのはやっていなくて、何かしら現実に起きない、そういったことを主に扱っております。例えば、初めて撮った長編映画『ローレライ』は、太平洋戦争末期に3発目の原子爆弾の投下を阻止するために反乱を起こす日本の潜水艦、という話ですが、もちろん、3発目の原爆なんてものはございません。

『日本沈没』でも、ご存知の通り現実の日本は沈没していません。『のぼうの城』は実際に戦国時代末期にあった出来事を映画化したものですが、文献によるとそうだった、という話しかないので、その隙間を全部肉付けしていかなければならなかった。『進撃の巨人』はコミックスを原作にした、まったく架空の世界、ファンタジーに近い話でした。
退屈な日常が破壊される瞬間
樋口 また、遥か昔から日本独自の空想で生まれたアイコンというものを、どう現実世界に同期させるか?現実世界にそういうものが現れたらどうなるか?をきちんと検証しながら作ってみたのが『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』という最近の2本です。
とまあ、かなり偏っているわけですね。なぜかというと、最初にやった仕事だからというのもありますが、特撮が好きだった。なぜ特撮に惹かれたかといいますと、まさに現実と非現実の境界を行ったり来たりするのが非常に楽しかったからです。
子供の頃に、テレビとか映画で、非現実的なものが映像に現れるのを見ると、その瞬間に「現実とはこういうもんだ」っていうルールが歪むんですね。言ってしまえば、退屈な日常が破壊される。子供ながらに抱いていた現実への欺瞞、願望が満たされる瞬間でもあります。
“怪獣”を裏打ちしていたリアリティ
樋口 一番はなんといっても、怪獣です。現実を写したお芝居の延長線上に、突然こういう想像上のものが現れる。当時はそこまでクオリティの高いものではありませんけれど、今でいうところのメディアミックス的なものによる補強がすごかった。例えば、本や雑誌の挿絵での解剖図とかですね。どんな内臓だとか、そんなのは別にテレビ番組の中では紹介されないんですけれども、それによって裏打ちされていくわけです。

私は1965年生まれですが、1966年くらいからは第1次怪獣ブームで、映画やテレビで色んなタイプの怪獣作品がこぞって作られました。そうすると今度はおもちゃが売れる。そして、先ほどの雑誌のように、どんどん世界観が掘り下げられていく。そういうのを見て、子供ながらに「現実にあったらこうなんじゃないか」というものがどんどん豊かになっていく。
さらに現実を混乱させるのが、デパートの屋上での怪獣ショーで。テレビの中にしかいなかったものが、本当に目の前に現れる。しかもそれがちょっとくたびれていたりするものですから、混乱に拍車がかかるわけですね。
娯楽としての“現実離れ”したシチュエーション
樋口 その頃の映像は、今見るとチャチなものかもしれないけれど、当時としては本当に現実の境目を超えてやってきたものだった。そもそも、現実離れしたシチュエーションというのは、我々の子供時代に限らず、100年以上前の映画開闢の頃から娯楽になりやすかったんですね。

人類初の映画、フランス人のリミュエール兄弟が作った『ラ・シオタ駅への列車の到着』は見世物小屋の中で上映されていました。何のことはない、ただ本当に列車がやってきて、お客さんが降りているだけの映像です。でも当時は、現実をそのまま写し撮って複製して、別の場所で上映するのは衝撃的なことだった。「なんでこの小屋の中に列車がやってくるんだ?」と大騒ぎをしたらしい。本当かどうかはわかりませんが、そう伝えられております。
それから、モンタージュ技法といって、カットとカットを重ねて何が起きているかを物語るようになります。1936年には、1906年に実際に起きたサンフランシスコ大地震を題材にした『サンフランシスコ』という映画が作られました。より刺激を求めて、大変なことが起きている。今だったらケガ人が出るからやるなって言われるような、本当に危ないことをやっています。

このように、災害の様子を映画で再現して、それを見世物にしていた。そういう災害や破壊、あるいは戦争というものは、映画の黎明期から多くのお客さんを満足させる主題になっています。
映画の歴史は技術と想像力のいたちごっこ
樋口 この段階で、映画は何をすべきかという運命が定められていました。それは、“視覚的な興奮”です。音も入るんですが、まず目に飛び込んでくる情報で人間の情動を動かすのが、映画の目的というか、一番得意とするものだったのではないかと思います。
そしてまた、飽きっぽい観客の要求はどんどんエスカレートして、それに合わせて内容も刺激的になっていきました。1933年の『世界大洪水』では、現実に起きていないこと、世界全土がダメになる大洪水が描かれる。それをどう映像化するか、という技術がどんどん発展するようになります。

1933年の『キングコング』ではコマ撮りが使われました。宇宙を舞台にした戦争ものである『スター・ウォーズ』(1977年)を作るためには、モーションコントロールカメラが、そして『ジュラシック・パーク』(1993年)では恐竜が現実にいるかのように見せるために、3DCGが実用化されました。
こうして、想像力とお客さんの要求、そして技術というもののいたちごっこがずっと続いているのが、映画の歴史と言えると思います。
破壊するために現実を精密に再構築する
樋口 ひるがえって日本では、我々の先輩たちが1954年に『ゴジラ』という映画を作り上げました。東京の街に現実には存在しない巨大な怪獣が現れて、現実を破壊し尽くすという映画です。
そのために何をするかというと、現実を精密に再構築しなければならない。そうしないと、その差分というものが刺激にならないわけです。本物に見えないものは、脳の中で「本物じゃない」となってしまう。それだとなんだか満足に届かないんじゃないかと思います。

1956年の『空の大怪獣ラドン』では、戦後復興して間もない博多の街がどんどん破壊されていきます。そのために、実在する街を徹底して取材して、写真を撮って、全部計測して、ミニチュアセットを組んで完璧に再現しています。
本物を作れない時は本物とすり替えろ
樋口 しかし、これには当然ものすごく手間がかかる。『ラドン』は『ゴジラ』の倍以上の予算がかかったと言われています。最初のうちはこうやって実験的にお金をかけさせてもらえるのですが、まあ、そんなに世の中というのはお金があるわけではございません。ちょっとでも安くやれないか?というのが世の常です。
『宇宙快速船』(1961年)は、子供向けにターゲットを絞ったSF、言ってしまえば低予算映画でした。でも、中身は本格的な地球侵略もので、前半の見せ場は敵の円盤による東京都心の破壊描写です。やらなければいけないことは大変、でもお金はない、どうすればいいんだ?と。
そこで、本物を作れないときは本物とすり替えろ、とまあ、こう発想したわけですね。破壊の瞬間まで実際の風景、本物を見せておいて、円盤が破壊光線を出した瞬間にミニチュアセットとすり替える。突然切り替わっても、その爆発する動きの中で、見ている人間の脳の中では「本物が爆発したんだろう」と誤認識しているわけです。

セットは壊すだけなので、そこまで精密なものでなくてもいい。それまでと全く違うアプローチで、もっと低予算で、しかも効果的な映像が作られるようになったのです。

ひっくり返すために現実を引用する
樋口 このように、現実に入り込んでくる非現実が娯楽になるのであれば、現実の割合を画面の中で多くして、ひっくり返るピースを増やした方が、驚いてもらえる効果が大きいのでは?と思っています。
現実を引用して対比させるのは映画だけではありません。TVアニメ『ルパン三世』シリーズの『さらば愛しきルパンよ』というエピソードがあります。演出が「照木務」になっているんですけれども、実はこれは宮崎駿さんの別名義です。

70年代末期の東京の風景を、アニメーションでかなり精密に再現し、そこに戦車が現れたらどうなるか?といったことを描いている。後に色々なアニメーション作家が影響を受けて、作品に現実的なものを取り入れるようになっていくんですが、かなり初期の頃にこうした描写を取り入れたのが、実は宮崎駿さんだった。
虚構の輪郭を際立たせるには
樋口 最後に、誰かが空想したものは本当にうつろいやすかったり、ふとしたきっかけで解けてなくなってしまう、その不安定な要素をどう取り除けばいいのか、を考えます。
やっぱり、今まで見てきたものでは、現実的な要素の中に一つだけ異物が入る瞬間、というのが一番おもしろかったなと感じています。虚構の輪郭をどう際立たせるのか、を絶えず考えているのですが、それは知らないもの、見慣れないものを、見慣れたものと同一画面に混在させることで、「これは本当にあるんじゃないか?」と錯覚させることができるのではないかと。それが今、我々がものを作っているときに、一番留意していることですね。
リアリティを生み心を動かす要素とは?
藤井 ありがとうございます。僕らの日常に一つ異物を入れると、そこから色んな波紋が広がっていく。それが面白いというのは、昔からなんですか?
樋口 面白いと思うものはそっちが多かったですね。逆に異物だらけの作品はなんとなくフックしない。例えば、ゴジラでも南海の孤島で怪獣が戦う、みたいな話もあるんですけど、そうなった途端に満足しなくなってしまう。やっぱり、自分たちが暮らしているようなところが大変な目にあうかもしれないというドキドキがあったほうが、自分は見ていて充実するというか。
藤井 でも『スター・ウォーズ』みたいなのはもう完全に異世界じゃないですか。あれは樋口監督にとってはどうなんですか?

樋口 あの場合はですね、世界の築き方とかがそれ以上に本物に見えたっていうか。『スター・ウォーズ』の場合、何が一番良かったかというと、スピード感なんですね。それまでの宇宙船は、のんびり画面の右から左へ横切っていく。ところが『スター・ウォーズ』の宇宙船は、それこそ点のように見える遠いところから手前にやってきて、カメラにぶつかるギリギリを通過していくという、自動車レースの中継みたいな画の作り方をしている。そのスピード感、挙動だけでリアルに見えるっていうのが画期的で。
現実的なものの構成要素って、光の陰影だったり、輪郭だったり、色だったりかと思ったら、あの映画から「動き」という要素がもう一つ増えちゃったんですよ。リアルに見える動きがあれば、そこにあるのが本物でなくてここまで心を動かす要素になるんだ、と。
物語は広げることではなくせばめること
藤井 なるほどね。あの、僕がVRの会社を始めて、360度を全部撮れるカメラを使うようになって、最初はすごく興奮したんですね。で、この中に色んな情報を埋め込んで、複数の物語を埋め込むようなことができる、と思ったんだけど、360度映像で物語を作る人があまりいなくて。
樋口 そうですね。実はある意味、物語って広げることではなくて、せばめることなので。
藤井 そうなんですよね。だから、ああ、面白いなぁと思って。結局、伝えたいことを伝えるためにカメラを使うのであって、丸ごとその場を体験してほしいわけじゃないんだなと。
樋口 もしかしたら、360度の中でも、こっちを見なさいよという視点誘導は必要なのかもしれませんね。例えば、テーマパークのライドも、実は見せたいものは作り手が選んでいるわけですよね。そこで何を見てもいいけれども、皆さんこっちを向いてくださいね、ガコーン、とかいって。でも、それが観客にとって無理やり見せられているストレスにならないように、というか。
藤井 そうそう、あと動くということはその分、見える範囲が小さくなるので、結局進行方向にしか注力できないんですよね。
“体験”と“物語”は違うもの?
樋口 あと、自分の中でまだ結論は出ていないんですが、物語が邪魔をしている可能性があるんですよね。なんだろう、体験と物語は親和性がよくないんじゃないかっていう。
藤井 “体験する”と“物語を楽しむ”ということは違いますか?
樋口 そう思うんですよね。ただ、その辺が上手い人もいますよね。例えば、ゲームを作るのが上手い人とか。今のゲームって体験的になっている中で、ちゃんと物語をそこに入れ込むことができる人もいる。
藤井 まあ確かに、嫌だよね。別に火山とか登りたくないよね、熱いから。
樋口 なんか竜に追いかけられたり、腐ったゴリラに追いかけられたりとか、嫌ですもんね。

藤井 そういう意味で言うと、樋口監督の作品はどっちなんですか?物語をみんなに楽しんでもらうんですか?それとも体験なんですか?
樋口 ギリギリ、自分は体験の方を優先しているような気がします。体験を絶えず入れていかないと自分の中でテンションが上がらないというか。やっぱり、驚いてもらいたい。物語って驚くというより、感動するとかであって。それよりはドキドキしてもらったり、ワクワクしてもらったりということを前提にしていて。「もうビックリしたでしょう?」みたいなことに喜びを感じています。
AIはこれからの映像制作にどう関与する?
藤井 受講者の方からの質問で、「AIがこれから何らかの形で映像制作やアニメーションに関与してくると思いますが、その点について樋口監督はどう思われますか?」と。
樋口 それを言ったら、セルで描いた女の子と結婚できるか、3DCGの女の子が恋愛対象になるかとか、そういうのと同じ気がするんですよね。自分はダメだけど、君たちが好きだったらいいんじゃない?っていう。
藤井 樋口監督がそうだというわけではないけれども、そういう作品が好きで、受け入れるんならいいよっていう。
樋口 ええ。結局、僕らが作っているものは、誰かが受け入れるから成り立っているものだと思うんですね。だから、自分が受け入れられないからそれはダメっていうのは、自分がやっていることも否定されちゃうような気がするので。
藤井 ツールの一つとして使う分には全然いいと思いますし。結局、作品って「俺が作った」ですものね。なんだかんだ言って。
樋口 AIが作ってくれるわけではなくて、作らせたのは俺だ、みたいな。プロンプトとかもあるわけじゃないですか。やっぱり、どうしてそれが生成されたかというのは、誰か神様がいるわけで。
樋口監督にとっての「#現実とは」
藤井 最後に、樋口監督にとっての現実とは、を一言でお願いします。
樋口 なんでしょうね。現実っていうのは「実家」みたいなものですかね。
藤井 実家?!
樋口 ええ、「家出した実家」みたいな感じです。やっぱり、どっかで帰んなきゃいけないんですよ。でも壊したいし。壊したいんだけど、壊したら元通りにしなきゃいけなかったりとか。それが実家だなっていう。
藤井 なるほど。わかりやすくていいですね(笑)
(テキスト:ヨシムラマリ)
