デジタルハリウッド大学と現実科学ラボがお届けする「現実科学 レクチャーシリーズ」。
「現実を科学し、ゆたかにする」をテーマに、デジタルハリウッド大学大学院 藤井直敬卓越教授がホストになって各界有識者をお招きし、お話を伺うレクチャー+ディスカッションのトークイベントです。
X(旧Twitter)のハッシュタグは「#現実とは」です。ぜひ、みなさんにとっての「現実」もシェアしてください。
概要
- 動画公開期間:2024年11月5日(火)~2025年1月5日(日)
- 視聴費用:無料
登壇者

池松 壮亮
1990年生まれ、福岡県出身。03年に『ラスト サムライ』で映画デビュー。近年の主な映画出演作に『斬、』(18)『宮本から君へ』(19)、『ちょっと思い出しただけ』(22)、『シン・仮面ライダー』(23)、『せかいのおきく』(23)、『白鍵と黒鍵の間に』(23)、『ぼくのお日さま』(24)、『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』(24)など。2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」では豊臣秀吉役を演じることが決定している。石井裕也監督作品には『ぼくたちの家族』(14)、『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(17)、『アジアの天使』(21)、『愛にイナズマ』(23)など多数の作品に参加しており、今作が9作目のタッグとなる。

藤井 直敬
株式会社ハコスコ 取締役 CTO
医学博士/XRコンソーシアム代表理事
ブレインテックコンソーシアム代表理事
東北大学医学部特任教授
デジタルハリウッド大学 大学院卓越教授
MIT研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダーを経て、2014年株式会社ハコスコ創業。主要研究テーマは、現実科学、適応知性、社会的脳機能の解明。
共催
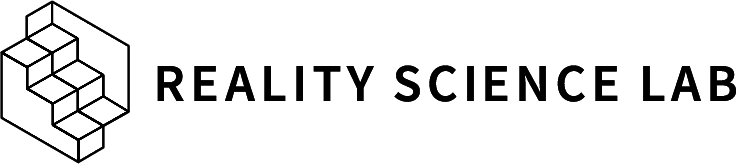
※本稿では、当日のトークの一部を再構成してお届けします。
映画『本心』誕生のきっかけ
藤井 本日は、現実科学レクチャーシリーズの特別編として映画『本心』を取り上げます。僕の友人でもあるAI研究者の清田純さんが映画『本心』のAI監修をされていて、そこから僕の方に「作品の中で使用するXRについて話を聞きたい」とお声がけいただいたご縁から、今回の企画が実現しました。
以前、原作を書かれた平野啓一郎先生にも本レクチャーシリーズにご登壇いただきましたけれども、今回はこの映画が生まれるきっかけを作られた池松壮亮さんをお迎えして、色々なことを伺いたいと思っております。

池松 この度、映画『本心』で主人公の朔也を演じました、俳優の池松壮亮と申します。よろしくお願いします。
藤井 池松さんはこの作品を映画にしたいと、ご自分で平野先生のところにお話をしに行かれたと伺いました。俳優さんご自身が許諾を取るようなことは、普通あまりされないのではないですか?
池松 最近になって少しそういった流れも出てきましたが、日本でやっている方はまだ少ないですね。僕が原作と出会ったのは2020年の夏だったのですが、撮影のために滞在していた中国のホテルで一気に読み終え、帰国して監督の石井裕也さんにお話しして、そこから割とすぐ2020年の暮れぐらいに、どうしても会っていただけませんか?と平野先生にお願いしました。
普段、俳優が行くようなことはないですし、変なプレッシャーになってあまり良くないかなと思いつつも、ひとつの説得材料にはなるかなと、監督とプロデューサーと3人で伺いました。そこで、こういう理由で物語に魅了されましたという話を僕からもさせていただいて。平野先生に3人の気持ちを聞いていただき、そこから1週間後ぐらいに、ぜひこのチームでやってください、とご連絡を頂きました。
明日かもしれない近未来
藤井 これって、原作は2040年が舞台の話なんですよね。それが映画では2025年から物語が始まります。時間軸が変わったのには、どういった経緯があったんでしょうか?
池松 僕が2020年に原作に出会った頃は、もうすぐにやってくるんじゃないかと思いつつも、まだ先の物語という感覚がありました。そこから撮影までに3年くらいかかっているのですが、その間にテクノロジーの急速な進化を素人ながらにも感じていました。
石井監督も同じようなことを思っていて、このままいくと2040年はもっと違う未来になっているんじゃないか?という話をしましたね。もう、街の風景も変わっているでしょうし、例えば空飛ぶ車があるんじゃないか、とか。そういう現実的なことを考えると、もっと前倒しにした方が良いのではないかと考えました。
あとはやはり2022年の末にChatGPTが広まったり、VRの撮影前にAppleのVRゴーグルが発表されたりと、どんどん現実がこの物語に寄ってきていることを実感しました。そういった中での判断だったと思います。

藤井 僕は、その判断はすごく正しいなと思いました。日常生活の中でAIも当たり前だし、リアル・アバターという新しい働き方もあったり、VF(ヴァーチャル・フィギュア)という新しいキャラクターが出てきたり、これって本当に近未来っていうか、明日起こる話かもしれないんですよね。なので、2025年に設定されたのは慧眼だと思うし、本当にこの公開のタイミングで観るのがベストだと感じました。
揺れる倫理観
藤井 実際に演技をされている時は、VFは見えないわけですよね?それに対して演技をする難しさや、違和感ってありましたか?
池松 ありましたね。亡くなった母親をVFとして作ってもらうということは、非常に今の感覚や倫理観からすると、ある意味神の領域に踏み込むということです。母親の愛情を懇願しながら作ることの複雑さ、現実と虚構の曖昧さ、そこに自分自身の願望が入っていることの怖さも感じました。
田中裕子さん演じる母親が、目の前で自分が思うように笑ってくれればくれるほど、やっぱり怖くなりました。そして何より触れられないことですね。じゃあ、自分の今の肉体は何なのか?と。シーンごとに複雑な気持ちがありました。
藤井 今の倫理観からすると超えちゃいけないラインがどこかにあるんだと思うんですよね。その葛藤は映画の中でも本当に表現されていて。だけど、その倫理観って日々変わっていくから、5年後には「なんでこの主人公はここで葛藤してるんだろう」って未来が来るかもしれない。
池松 そう思います。
藤井 亡くなった人たちをVRで再現して会話するというサービスも、すでに本当に世界中で始まっていて。利用する人はいろんな気持ちで利用していると思うし、提供者の側だって「みんながそれを求めているんだから何が悪いの?」って言っているので。倫理観というのは、今後本当に揺らいでいくんだと思います。
少し先の未来を通ることで気づく人間の悲しみ
藤井 映画のトレーラーの中で「革新的ヒューマンミステリー」という言葉がありましたけれども、僕は個人的に、ミステリーというよりは社会の仕組みや人がどう変わるのかというところにすごく興味があって。池松さんは、作っている途中で気づいたこととか、新しく思いついたこととか、そういうことはありましたか?
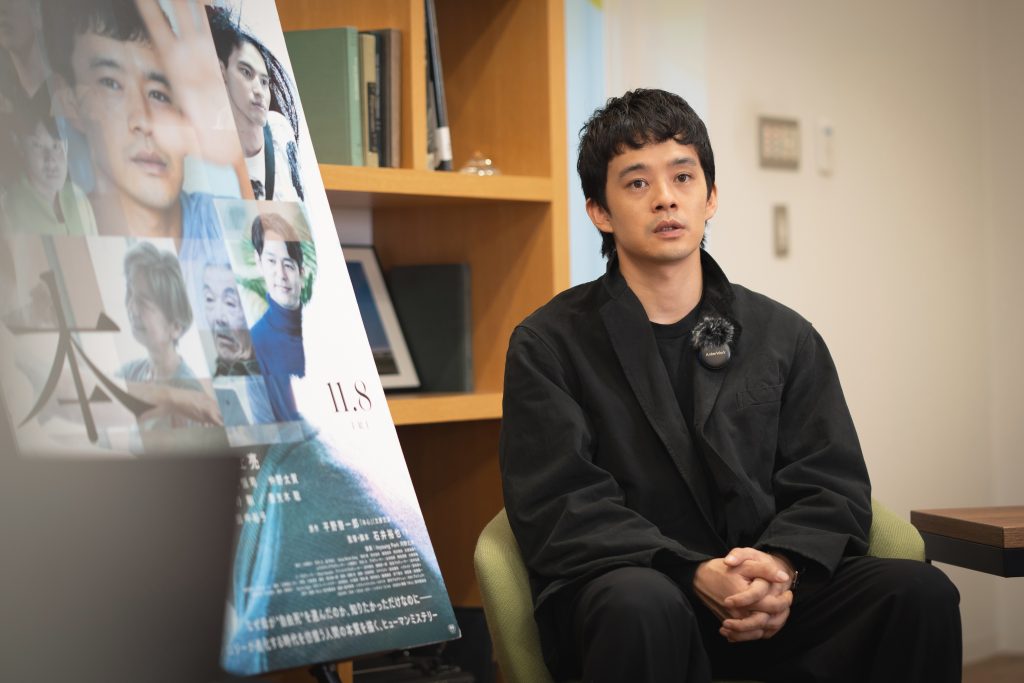
池松 ちょっと話が飛躍するかもしれないんですけれども、総じて感じたのは、どんな時代にもついて回る…人間が生きるうえで抱く悲しみのようなものに触れた感覚はありましたね。
藤井 今まで俳優としてたくさんの作品に出られていますけれども、それはその中でも新しい何かなんですか?
池松 そうかもしれないですね。この作品が近未来という設定だったこともひとつあったと思うんです。演じながら、仮想の空間というか、物語に入っていくような感覚があり、そこで朔也が世界の悲しみに触れながら、それでもやっぱり誠実に生きていこうとすること。自分のアイデンティティだけではなく、そこから飛び出た他者性に向き合いながら生きていくこと。そして、生きている実感を求め続けること。そういうことに、希望を感じましたが、エピソードを重ねるごとに「ああ、人って悲しいな」と感じました。
藤井 朔也はお母さんを再現することで今まで閉じていたドアが開いちゃったんですよね。一部には喜びもあったと思うんですけど、そこから何か見えてしまった。何か新しい悲しさにつながっているのかもしれない。そこは本当に、見ていて苦しいというか、「ああ本当、世界ってこうだよなあ」って思っちゃいますね。
現実と虚構が曖昧な世界の物語
藤井 今、テクノロジーが僕らの現実と虚構の世界の境界をぐいぐい動かし始めています。朔也がお母さんを再現するのとはまた違った、知らないうちに僕らの生活に介入して操作するという世界が、フェイクニュースなども含めて、もう始まっていると思うんですが、そういう世界で物語を作るっていうのは、どういうことになるんですかね。
池松 もう、物語というものが最後の手立てではないか、とすら思っています。
藤井 最後の手立て、ですか。

池松 今、藤井先生がおっしゃったように、これまでは現実と虚構の境界が、しっかりあったと思うんですよね。でも、その感覚がどんどんテクノロジーによってなくなり、自分たちが認識できなくなっていく。さらに、AIに物語そのものが取って代わられると、もう太刀打ちできないのかなと思います。
でもやっぱり、いつの時代も人間の神話が文明を作り、時代を作ってきたことを思うと、本当に物語の重要性を日々感じています。コロナのことにしても、ガザやウクライナのことにしても、それ以降さらに物語がいかに人間にとって重要か、必要かを感じることになりましたし…そんな神なき世界で、物語は世界を動かしていく最後の手立てじゃないかなと、そう思っています。
藤井 今の僕らって、毎日すごい量のテキストを消費しているじゃないですか。だとしたら、良い物語を食べたいなって思うし。それはAIが作る物語かもしれないし、本当に起きている物語かもしれないけど、やっぱり良い物語とか、人が幸せになる物語を食べたいし、みんなに食べてほしいなって思うんですよね。AIは人より良いものを作っちゃうかもしれないけど、大事なのは人を幸せにすること、人の内面を豊かにすること。それが今後、僕らが目指すべきことなんじゃないかと思います。
AIと人の共存のあり方
藤井 AIに負けちゃうとか、そういうのではなくて、例えば将棋やチェスではAIと一緒にプレイしますよね。ああいう形で、物語を人とAIなり、人工的なシステムなりが一緒に作って、「それは思いつかなかったけど、面白いね」っていうのができると良いんじゃないかな。
池松 そうですよね。AIがどのくらいのスピードでもっと身近になって来るのか、あるいは脳や体内に入ってくるのか。どういう倫理観を持ってそこに手を出していくのか。AI監修の清田さんがおっしゃっていて面白いと思ったのは、やっぱりAIと人間の共存のあり方はここ10年でほとんど決まるでしょうから、たくさん議論があったほうがいいと。そうか、10年で決まるんだ、と思って…。
藤井 あっという間ですよね。
池松 本当に、そうですね。
藤井 そこはちょっと怖いですけど。変な、破壊的な方向に向かわないでほしいというのが、みんなが一番に望んでいることですよね。今まで二千年、三千年と人はバカなことばかりしていたんだけれども。今の豊かさって、無尽蔵に利用可能な計算やデジタルのリソースだったりするから。そこをうまく使って、全ての人が幸せになれる世界というのを作れると僕は思っていて。そう考えた時に、社会をどう構築すればいいのか。僕はそこにしか希望がないですね。だって、奪い合ったらもう殺しあうしかないじゃないですか。

池松 面白いですね。新しい時代のヒントのように感じました。
作品の中でどうしても残したかった部分
藤井 映画はどうしても2時間の尺の中に収めないといけないから、平野先生の原作をそのまま作るわけではないと思うんですね。あの中で語られている、テクノロジーであるとか、倫理観であるとか、社会的な課題であるとか、そういうものを整理して取捨選択される中で、ここだけは絶対落とせなかったっていうのはありますか?
池松 もう本当に、どこを切るのも嫌というぐらい原作が素晴らしくて。テキストの、外側だけをもらっても上手くはいかないので。真髄に漂っているもの、読後感は同じでも、通るところは映画的なエモーショナルな感覚がないといけないので、そこは石井監督がほとんど選んでいました。
仲野太賀さんが演じるイフィーという役をなくした段階の脚本があったんですけど、平野先生とのやり取りの中で、それはどうしても入れてほしいというお話はありましたね。ネタバレになるのであまり言えないんですけれど、イフィーは世界のいろんな境界線、格差や、人間の身体性、そういう色々なボーダーをくっきりさせる役なので、そこは入れることになったと聞いています。
藤井 確かに、映画を思い起こしてみると、イフィーのシーンがなかったら、彼が登場しなかったらと考えると、厚みがなくなるというか、もっと暗い感じになってしまうかもしれませんね。イフィーがいろんな要素を持っているから、次元がぐんと増えるじゃないですか。
池松 僕は最初に原作を読んだ時に、母を作ることで2時間になるイメージがあったのですが、石井監督の中でうまくいかなかったようで。僕も、もうちょっと行きたいなというふうに感じて、その感想をお伝えしながら、今の構成になりました。
やっぱり、現実にある不確かな境界線と、あらゆる問題。いろんな、あらゆる要素に囲まれながら、その本心を巡る旅のように、未来で迷子になっていくイメージ。そういうふうにしていくことで、映画を観終えた時に立体的なエモーションが残るようにしたかったんです。結構いろんな要素があるので、すべての要素が入ってこなくても、エモーションだけで観られるような、そういった映画を目指せれば良いかなというふうに、考えましたね。
今の僕らのふるまいが2年後、3年後、10年後を作っていく
池松 先ほど「革新的ヒューマンミステリー」という話が出ましたけれど、日本では「社会派」と言ってしまうと、どうしても難しいと思われがちなんですよね。でも僕としては、やっぱり社会的なエンターテインメントにまず触れてもらうことで、そこから議論が起こるようなお話にできればと思いながら演じていました。
藤井 お話を伺っていたら、5年後、10年後にこの作品を観たときにも、結構重いものが残るんじゃないかなという気がしてきました。結局、何千年前からやっている物語、人の悲しさの物語がいろんな形で含まれていて。お互いがこう、色々な形でつながっているんですよね、本当に。
池松 ありがとうございます。近未来というものを通るからこそ、今ある問題、これからやってくる問題が際立つような物語になればいいな、と思っています。

藤井 原作の「本心」を読んでいらっしゃらない方々もこの作品をご覧になると思いますが、そういう方々にこの映画をどのように観てほしいですか?
池松 同時代を生きる人に、自分ごととして見てもらえたら、映画化した甲斐があると思いますし、幸せだなというふうに思います。少し先の未来で、朔也という主人公がどのように生きているか、何に喜んで何を悲しんでいるか、そういうところを見ていただければと思います。他のキャラクターたちもいかにして生きているか、その少し先の未来をのぞきながら、これからのことを考えるきっかけになれたらいいなと思っています。
藤井 今、池松さんがおっしゃったように、同時代を生きている僕らが一緒に考えて、その僕らが未来を作るんですよね。これからどっちに行くかわからないけれど、多かれ少なかれ僕らの振る舞いが2年後、3年後、10年後を作っていく。だとしたら、これはやっぱり考える良いきっかけだと思うし、実際にもう起きているから。それに対して、自分はどう貢献してより良い未来を作るのか、というところに皆さんの思いが至ったら面白いですよね。
池松 本当に、そう思いますね。
池松さんにとっての「#現実とは」
藤井 最後に、池松さんにとっての現実とは何ですか?
池松 正直に今ある気持ちをお伝えすると、やっぱり分からなくなりました。でも、藤井先生とお話しして…いつだって現実を決めてきたのは人間の記憶、自分自身の記憶なのかなと。自分自身の記憶が現実と認識すれば、それが現実になってきたのではと思います。
藤井 記憶というものが、今ここの現実というものの履歴として残っていく。それを振り返ったとき、あの時の現実は僕のこの記憶だったと、そういうことですね。
池松 ありがとうございます。わかりやすく説明していただいて。
藤井 本日はありがとうございました。

(テキスト:ヨシムラマリ)
本レクチャーのアーカイブはReality Science LabのYouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。

